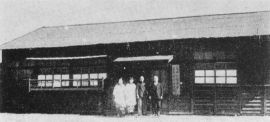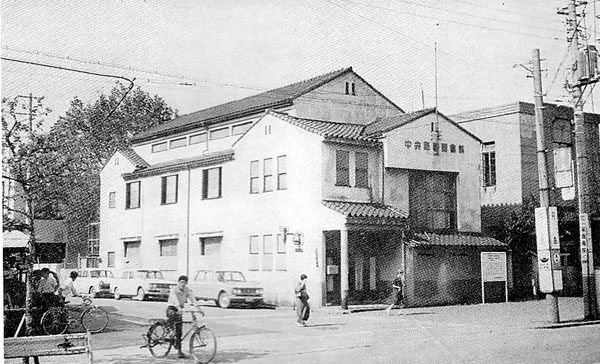- 本会は1911年(明治44年)に京橋区医会として発足し、1916年(大正5年)に京橋区医師会として改組された。
- 1874年(明治7年)の医師法公布により医師免許制が確立され、1906年(明治39年)に内務省令第33医師会規則が発布された。
- 1919年(大正8年)に勅令第429号医師会令が発布され、翌年、東京府にも郡区医師会、東京府医師会が誕生し、現在のような統一された医師会形式が整った(医師は全員強制加入)。
- 1923年(大正12年)9月の関東大震災直後、医師会を挙げての救護活動を展開、月島の救護所は月島簡易診療所として昭和9年から京橋区医師会に委譲されて経営。
- 1939年(昭和14年)10月、紀元2600年記念事業として会員の寄附金での月島簡易診療所改築と医師会館併置を決定。
- 1940年(昭和15年)に京橋区医師会館を竣工。地区医師会としては最初。しかし1941年(昭和16年)に太平洋戦争が勃発、医師会館は憲兵隊の屯所となり、医師会の資料は散逸した。
- 戦時色一色となった1942年(昭和17年)に国民医療法公布、勅令により医師会は改組することになり、従来の医師会は解散。京橋区医師会は東京府医師会の京橋区支部となり財産は全て東京府医師会に供出、会長、理事は支部長、幹事と改称された(1943年(昭和18年)7月の都制施行で東京府は東京都に)
- 1945年(昭和20年)の終戦後、医師会の一部改正の勅令が公布、役員は公選制になった。月島の医師会館も返還され、医師会の事務所となった。
|
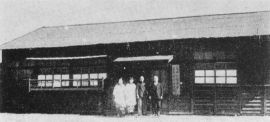
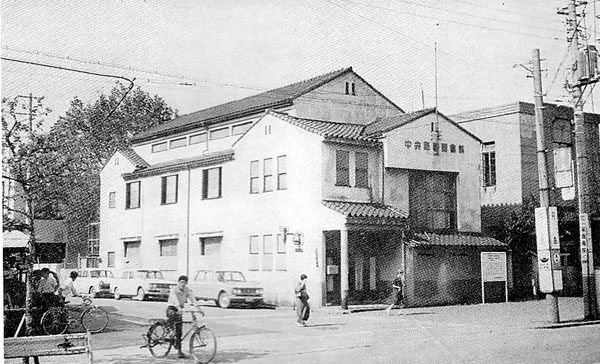 |
- 1947年(昭和22年)11月28日、社団法人中央区医師会誕生。
- 1945年(昭和20年)5月には一行政区一医師会という制度となり、戦後、京橋区が日本橋区と合併して中央区となった為、京橋支部も日本橋支部とともに一医師会設立の準備を進めた。GHQの指令で医師会も強制加入の財団法人から任意加入の社団法人に改組された。
- 1950年(昭和25年)4月頃、母性保護医協会から優生保護法指定医になるには地区医師会長の推薦が必要との権限が与えられ、会員が増加(この頃、整備委員会の前身の審査会発足)。
- 1952年(昭和27年)3月、中央区医師会と日本橋医師会に円満分離。
- 理事会で総論賛成、各論反対が続出し、原因は行政組織が各区に残存(保健所2、税務署2、社保事務所2)している為と判明。話し合いの結果、医師会も個別対応が良いとなった。
- 1954年(昭和29年)、準看護学校を開校、昭和36年に閉鎖(東京都医師会の中で開設も閉鎖も第1号)。
- 1961年(昭和36年)5月、会館再建準備委員会結成
- 1973年(昭和48年)9月、会館建設基礎調査委員会発足。1977年(昭和52年)新会館誕生。
|
- 1948年(昭和23年)11月、中央区医師同志倶楽部創立
- 昭和27年:中央区医師政治連盟と改称、昭和51年都医連の中央区支部と改称。
- 1950年(昭和25年)3月、中央区医師会2の部から武見太郎日医副会長誕生。
- 1957年(昭和32年)4月、武見太郎日医会長が誕生。
- 1961年(昭和36年)2月、医師会、歯科医師会の全国一斉休診実施。同年7月、医療危機突破中央区医師大会、同年7月保険医総辞退回避。
- 1981年(昭和56年)4月、武見太郎日医会長引退、同12月に逝去。
その後の歴史
- 鈴木肇先生と中央区医師会(05/2/3:若手の会資料)、
- 中央区医師会の活動(平成17年度以降)
|
 |